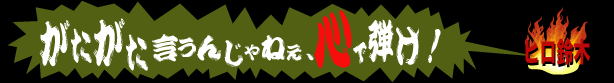2006年07月11日
第31回:ワールドカップ・サッカー

ガタガタ言ってねぇで、
ここまで這い上がってきて勝負してみやがれ!
***ドイツ・ワールドカップ・サッカーの決勝戦を見終えた。いやなんとも、やりきれない終り方をしたな、そんな気分で一杯だ。ウクライナ戦あたりから「このチームはまとまってるなぁ...」と思わせ、準決勝のドイツ戦での終了土壇場2得点では、「ちょっと神ががってきたかも。」と思わせたイタリアも、劣勢を予想された最後のフランス戦では粘って粘って、我慢しまくって優勝をもぎとった感がある。でも一体、ジタンはイタリアの選手にあそこで何を言われたのだろう?「マエストロ」とさえ呼ばれ、ベスト2にまでチームを導き、今ワールドカップ最優秀選手に選ばれた世界最高峰のプレーヤーである彼が、決勝戦の、それも延長後半戦、こともあろうに彼自身の引退試合、最後の最後である。映像を観る限りでは、プレーそのものとは全く関係ない範囲での、あまりにも個人的で見るに耐えない「ケンカ」にしか見えない。ちまたの噂では、相当ひどいことを言われたらしいのだが、それでもなんとかしてその怒りを抑えて最後まで戦い続けて欲しかったと思うのは俺だけだろうか。せっかくここまで楽しませてもらったワールドカップ2006、ちょーっとだけしょっぱい終焉だった。
今までサッカーというスポーツには全くといっていいほど興味がなかったが、今回のワールドカップで完全にはまった。やはり決勝リーグに入ってからは、どの試合も見ごたえがあった。ブラジル、フランス、アルゼンチン、イタリアなど、ヨーロッパや南米の強豪同士の試合は、得点数に関わらず見ていて全く飽きが来ない。神業のような個人プレー、研ぎ澄まされたチームプレーが、ものすごいスピード感で展開される。
まずは同じ目的の前に集まり、その目的達成のためには何をどうすべきか試行錯誤が繰り返される「個」が強靭であればあるほど意見の食い違いや主義主張のぶつかり合いは激しさを増すのは当然だろうし、それら一つ一つを回避せず尊重し、共通の目的を達成するために一人一人が貪欲に回答を模索するプロセスでチームは成熟してゆくのかもしれない。「和を以って尊しとす。」とは美しい言葉だ。でもこの言葉を言い訳にして感情のぶつけ合いを面倒臭がり回避し、「個」の存在をはなっからけむたがり結果的には少しもお互いを高め合えずにいるとしたら、それでは「井の中の蛙」とか、「傷の舐めあい」とか、「ダブル・スタンダード」とか言われ続けても仕方がない。ブラジルに完敗した後の日本チームの選手たちがグラウンドを去ってゆく姿やインタヴューに答える「熱くない」表情が印象的だった。それにワールドカップのためという、ごく短い期間内での集団行動にもかかわらず、チーム内にはいくつかのグループが出来ていたらしい。出場が決まったときに「俺がこのチームを勝たせてやる。」とムキになり、世界の前に完膚なきまで叩きのめされて「ちきしょー!!!」と悔しがり、そして「次は絶対にこの俺がこのチームを優勝させるぞ、バカヤロー!」と4年後のリベンジを誓った選手が一人でも多くこの中にいることを願いたい。
試合後にただ一人グラウンドに仰向けになり、目を真っ赤に腫らしてしばらく動かなかった選手がいた。この中田英寿という選手は、ヨーロッパのリーグでも知る人ぞ知る、日本サッカーの中では群を抜く優秀なプレーヤーなのだそうだ。プロサッカー選手の現役寿命がいったい幾つくらいなのかは知らないが、若干29歳の彼が自分の意に反してチームの中心的な存在に立たされ、他の選手達との意思の疎通がうまくゆかず孤立し、それが結果的に惨敗の一因になったことへの責任を感じていたらしい。また彼は「プロになってからは『サッカーが好きだ』と素直に言えない自分がいた。」とも言い、若干29歳で引退を決意し、もうプロとしてボールを蹴ることは絶対ないだろうと言い切った。もともと言葉の少ない方なのだそうだが、途方もないプレッシャーだったのだろうし、泣くほど悔しかったのだろうし、「自分=個」と「チーム」との位置感、距離感のとり方をめぐる、周囲と彼との間にれっきとした形で存在する途方もなく大きな違いに歯がゆい思いをし、戸惑い続けたのだろう。
「二十歳までに世界中の主要コンクールを渡り歩き、人々の記憶に残る結果を残せなければ、クラッシック音楽のシーンでプロ・ピアニストとして成功するのは100%無理。」...以前、クラッシック・ピアノを教えている友人からそんな話を聞いたことがある。随分と難儀な世界だなぁと、全てのクラッシック・ピアニストに同情してしまった。こっちとら、四十、五十代のデヴューだって稀じゃないブルース・シーンである。いったいぜんたい、はたちそこそこのガキが大人相手に「いかせ」られる訳がねーじゃねーか、などと鼻っ先でせせら笑ってしまいたいところだが、やはりそこは高貴なクラッシック音楽のシーン、とてもじゃないが尾籠な音楽にどっぷりと浸る俺達下々の輩には到底理解不可能な現実があるに違いない。そういえば昔、日本の歌謡番組かなにかで、淡谷紀子さんが若いアイドル歌手に「人に聴いてもらえるような歌は三十を越えなきゃ唄えないものなのよ。」と優しく語りかけていた。さすがは「ブルースの女王」、説得力がある...と思うけど...どうかな...。
かつてはニューヨークに住み、ニューヨークのブルース・シーンやロック・シーンでは超売れっ子ドラマーで、現在はボ・デイドリーや竹中尚人(チャー)とコンスタントに活動し、今年2月には俺のバンドG.J.JUKEの東京での演奏でドラムを叩いた嶋田ヨシタカ氏が以前、「時々自分が、本当に音楽が好きで音楽をやっているのかどうかがわからなくなる時がある。」と、一緒にビールを飲みながら話してくれた事がある。その時は口には出さなかったが、「ああ、(そう感じるのは)俺だけじゃなかったんだなぁ...」と思ったし、同じように感じているプロミュージシャンは周りに何人もいることがわかった。やはりニューヨークでは有名なセッション・ベーシストの友人が笑いながら“Of course, Hiro, because we’re professionals.”「当り前だろ、俺達はプロなんだから。」と言っていた。
1999年にノルウェーをツアー中、南西海岸のあるライヴハウスでの演奏後、「音楽を本当に愛しているのならもう一度演奏しろ!」と、遅れて入ってきた酔っ払いがなんともかったるいインネンをつけ始めた。「おぅ、やってやるよ、2000ドル払え。」とメンバーの一人が冗談半分に言い返すと、「オマエらは金の為にしか音楽ができねぇか?!」と今度は俺にしつこくからんできた。(こういうケースでは、絡まれるのはまず間違いなく俺だ。よっぽど喧嘩が弱く見えるのだろう。)するとバンマスが俺とその酔っ払いの間に割って入り、「ぅるせぇー、大きなお世話だこのヤロー、金払えねーんだったらとっとと出てけ!」と思いっきり顔を近づけて怒鳴り散らし、そいつの胸ぐらを掴んで外に引きずり出した。まったくその通り、「大きなお世話」なのだ。誰が「プロ」を名乗ろうと、自分の演奏にいくらの値段を付けようと、他人の知ったこっちゃない。そして聴く側はその値段に納得すれば払って聴けばいいし、高いと思うなら聴かなければいい。単純な話だ。もちろん、俺達は金だけが目的で音楽をやっているのではない。しかし時には自分の情熱を注ぎ込めないような演奏を自分に強いなければならない状況に置かれることもあり、それは結果的に傍からは「金の為の演奏」と見られてもいたしかたない。プロと名乗る以上、自分の生きざまを音楽という「壁」に思いっきりぶつけて、自分自身に跳ね返ってくるものは好むと好まざるに関わらず全て引き受ける責任と覚悟がいる。常に金と名声と充実感ばかりが跳ね返ってくる、気持ち良いだけの「壁」など、どこのプロの世界にもないのではないだろうか?
14年前、ろくに英語も喋れず、右も左もわからないままこのNYにやって来た。世界一大きく、同時に世界一の音楽の街で、一年の滞在という期間限定でこの街の音楽を徹底的に楽しもうと、僅かな貯金から得たトラベラーズ・チェックとギター一本を肩に。最初に転がり込んだ宿はミッド・タウンの西にある月850ドルの長期滞在用ホテルだった。ここでプロとして生きてゆこうなどという気持ちは微塵もなかった。音楽を将来の仕事と考える余地など全くないほど、この街の音楽はレベルが高いと信じていたし、だからこそ音楽をとことんピュアに楽しめるはずだと信じていたから。まずはとにかく必要最低限の情報を得ようと、足を運んだのはマンハッタンのはずれにあった日本人がよく出入りすると聞いたライヴ・ハウス。そこでは毎晩ライヴ演奏がおこなわれていて、従業員や出演ミュージシャン、そしてやってくる客も確かに日本人が多かった。同じ言葉を喋る者として、同じ音楽好きとして、一日も早く友人を作り、情報を得ようと最初は積極的に足を運んだものだが、新参者である俺の何かがよほど気に入らなかったようで、特にそこに出入りしている日本人ミュージシャン達から非常に冷遇され、まともな情報はほとんど得ることが出来なかった。またその店で聴いた彼等の演奏はというと、俺がミュージシャンとして東京でささやかながら積んだ経験と比較をしてみても、自分が抱いていた「プロ・ミュージシャン」のイメージからは程遠いものだったと言わざるを得なかった。結局、「ここは自分の来る場所ではない。」との大きな教訓を一つ得て、次に選んだ情報収集の場は地元の楽器屋だった。
ブリーカー・ストリート西にあるMU楽器やチェルシー・ホテルの隣にあるC中古楽器、スタッティン・アイランドのMB、そして48丁目の楽器屋街でニューヨークの情報誌ヴィレッジ・ヴォイスを片手に質問すると、ほとんどの店員達、そして来客までが先を争うようにお勧めのライヴ・ハウス(クラブ、バー)を紹介してくれた。どこの店が何曜日にジャムをしている、いや、あそこよりあっちの方が良いプレーヤーが集まるぞ、だとか、あの店のハウスバンドのギタリストは俺の友人だから声をかけてみろ、とか、あそこのバーテンダーはイイ女だぞ、とか。それらの情報をとりあえず鵜呑みにし、ギターを肩に恐る恐る「ライヴハウスはしご」をしてみると、それらのほとんどが地元の酔っ払いやジャンキー、ドラッグディーラー達の溜まるそれこそ薄汚い場末のブルース・クラブで、しかし地元のミュージシャン達を中心に熱のこもった演奏が毎晩のように繰り広げられていた。彼等の知名度はけっして高くないし、テクニック的に飛びぬけたプレーヤーがひしめいているわけでもない。それでも彼等の存在感、彼等の演奏、そして暗くて酒と煙草と汗の染み付いた店にうごめくオーディエンスの、三者がぐしゃぐしゃに絡み合って創りだすグルーヴは紛れもなくニューヨークのグルーヴそのものだったし、突然店に入り浸り始めた変な日本人ギタリストに対しても彼等は身構えたり見下したりすることは全くといっていいほどなく、オープンマインドでリスペクトフルでしかもちゃんとお互いの距離を保ちながら接してくれて、いつどんな時間に顔を出しても「よう、来たか!」とタダ酒をふるまって歓迎してくれる、気の置けない店ばかりだった。残念ながらそれらのライヴハウスのほとんどが潰れてしまい、働いていた店員たちも今どこで何をしているのか全くわからないが、でもそれらの店を最初に紹介してくれたいくつかの楽器屋はどれもまだあの頃と同じ店長や店員達によって営業されていて、今でも「よう、まだ生きてたか!」と歓迎してくれるし店でいくらうろちょろしても放っておいてもくれる。
そんないわば土着のライヴ・ハウスで日本人のミュージシャンがプレーするのを見るのはとても稀なことだったが、コラムでも何回も触れているドラマーの嶋田氏や、もう20年近くこの街NYでプロ・コンポーザー、キーボード・プレーヤーとして大活躍されるT氏、そしてかつてはアトランティック・レーベルのレジェンド達と対等に渡り歩いたベーシストのTH氏等、経験豊かで素晴らしい才能を持った日本人ミュージシャン達とはこれらの店である日偶然に出会っている。そして彼等に共通していることは、音楽には常に真摯で厳しく取り組み、年齢や経験や出身に一切関わらずお互いを尊敬し、しかし「一匹狼」を地でゆく強烈な「個」であったということだ。
自分がミュージシャンとしてどこまで通用するのか、もう一度だけ試してみようと、ニューヨークで本格的に音楽活動を始めてから約2年後、ある日系の企業でアルバイトしたとき、そこには同じようにミュージシャン志望の日本人が複数、常に働いており、しばしばフライヤー(チラシ)などを会社に持ってきては自分達の関わるギグを同僚社員たちに紹介ていた。その職場で働いている社員達はみんなとても仲がよく、そういった「身内ギグ」には時間の許す限り誘い合わせて足を運んでいるようだった。働き始めてから2ヶ月位たってからだろうか、俺も試しに、と、ブロードウェイとハウストン・ストリートの交差点に程近い「ルイジアナ・バー」という店でのカントリー系ロック・バンドとのギグへ同僚社員達を招待した。ルイジアナ・バーはキャパ100人位のレストラン・バー兼ライヴハウスで、クロウ・フィッシュやキャットフィッシュ、BBQなどの南部料理を出す、アンティークなガソリンスタンドを模したような内装の、当時はかなり人気の高い店で、当日は同僚達が、親しい友達やパートナーを伴って10名くらい、満員の店内へ押し合いへし合いしながら入ってきてくれた。演奏も店も気に入っていただけたらしく、お酒も随分と進んでいたようで、誘った甲斐があったとホッと安心したものだが、後日「従業員がみんなアメリカ人、ミュージシャンもスズキさん以外みんなアメリカ人、客も私たち以外みんなアメリカ人で、あんなライヴに行ったのは初めてで、びっくりした。」という何人かの共通した感想がとても印象的だった。その後も彼等の何人かは俺のコミットするギグにコンスタントに顔を出してくれていた。今となっては随分昔の懐かしい思い出である。
そんなコテコテの地元ブルース・クラブにも、俺が最初に何も知らずに足を運んだ「日本人の多く集まる店」のミュージシャン達が客としてごく稀にやってきては先輩風を吹かせながら演奏にケチをつけたり馬鹿にしたりしていたことがあったし、その後もインターネットの日本人の開いている掲示板とかに匿名で集まっては俺や俺の関わるバンドやメンバー達、親しくしているミュージシャン仲間、そして演奏している店やコンサート等を言いたい放題こき下ろしたり、営業妨害やハラスメントに相当するような誹謗中傷をあることないこと書き連ねていたと聞いた。そして最近になってももまだ同じような事をやっている連中がいるらしい。しかしそんな彼等が、俺や俺の音楽仲間たちが日頃から音楽と格闘し今日一日を食いつなぐために必死になってあぶく銭をかき集めているこの「場末のグラウンド」にやってきて真っ向から勝負を挑んできたためしは一度もない。彼等が肩を寄せ合って酒を飲んでいる場や演奏の場にたまたま偶然出くわした時も、彼等の言葉や音は相変わらず淡白でうつろで毒気が薄く、それらは聴いているこちら側に届くはるかずっと以前に失速していた。
帰国の際には必ず立ち寄るいくつかのセッションやジャム・セッションで、プレーする曲をメンバーに説明しそれぞれのパートに指示を出したりすると、腹を立ててしまったり、聞こえているのかどうか疑わしくなるほど存在感の薄いプレーヤーが多いのに気がつく。お互いをプレーヤーとして尊重し合い、共同作業でこれからクリエイトしてゆく音楽を少しでも良いものにしようとするからこそお互いの意見をぶつけ合おうとしているのに、いきなり個人的な感情が先立ってしまったり、自分の気持ちをうつろな砦で囲ってしまってはそこから先に何も進めることは出来ないだろう。
もう少し具体的に言うと、例えばある都内ライヴハウスでのセッションでシャッフルの曲をリハーサルしていたとき、ベーシストが「ブッブ ブッブ ブッブ ブッブ」と三連の頭と裏を両方弾いていた。「この曲では裏は弾かずに『ブン ブン ブン ブン』と4分音符だけで弾いてくれるかな?裏を弾いちゃうと俺の創りたいグルーヴとは少し違ってきちゃうんだよね。」と意見すると、そのベーシストは急にむっとして態度が悪くなり、「フン...弾き方がちがうんだってさ...」と、独り言を、それも周囲に聞こえる声で吐き捨てるようにつぶやき、その後はリハーサル中も本番中も俺とは一切視線を合わせず、言葉を交わそうともしなかった。結局その晩は最後まで俺の意見だけが宙ぶらりんになったまま、彼ばかりではなくほとんど全ての参加者が何も言おうとしない、ずいぶんと質感に欠ける物静かなセッションで、俺もそれ以上は何も言わずにやりたいようにやってもらい、終了と同時に楽器を片付けてさっさとその店を出た。
ある新聞のスポーツ欄に今回のワールドカップについて、「チーム・ワーク、組織力で個々の弱さを組織で補おうとする従来の考え方では、日本はもう対抗できないのかもしれない。個人でも世界レベルに追いつく努力をしなければ、4年後も惨敗を繰り返すだろう。世界と日本との差は開いた印象だ。」とあった。「個々の弱さ」そして「世界レベルの個人」を指摘するここで筆者の言う「個」とは、フィジカル面だけでなくメンタル面での日本と世界との差をも指摘しているのだろう。でも簡単に「努力をしなければ...」と言うが、これは非常に難しく長い時間のかかる大仕事なのではないだろうか?これからあらゆる分野で活躍するであろう若い世代よりも、むしろ彼等を育ててゆく日本社会の方がどこまでこの「努力」についてゆけるか、どこまで成熟できるのかが、かなり心配だ。突出した才能に恵まれ、なおかつ強靭で凛とした「個」に成長した者は、誰が止めたところでどこへでも勝手に羽ばたいて行くのだから問題にはならない。問題は、惜しくも羽ばたけなかった「個」達がやはり同じように、この日本という受け皿の上でどこまで自分を信じ人を愛せる「個」として大人になれるか、そっちの方が遥かに難問だと思うし、実際この問題を解決しあぐんでいることに、日本はやっと危機感を抱き始めたところなのではないだろうか。まずは日本という社会が他の国や他の文化の物真似ではない、日本なりの方法で回答を見つけだし、それに基づいてどこまで面倒臭がらず根気よく努力を続けられるかにかかっていると思う。自分自身をちゃんと引き受け、生身の自分と名前に誇りを持てる「個」がどこの分野にも増えて欲しい。そうじゃなきゃ、つまらない。
気が遠くなるほど時間がかかりそうだが、始めないわけにはゆかない...よなぁ...。

引き受けてもらうから集まるんじゃない。引き受けるから集まる。責任はいつでも重い。
投稿者 hirosuzuki1 : 2006年07月11日 16:09