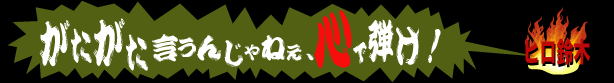« 第28回:2006年日本(その1) | メイン | 第30回:2006年日本(その3) »
2006年04月21日
第29回:2006年日本(その2)
***2月17日から28日まで、7本のギグと3本のラジオ出演、そして御大塩次伸二氏のギター・クリニックと、東京、神戸、大阪、京都、横浜、藤沢の間を12日間で一気に走りぬけた。いろいろなところで、いろいろな人の前で、ギターを弾き、歌を唄ったが、その中でも、オリジナル曲をめぐる、とりわけ印象深い出来事から話してみたい。
この7本のうちの5本がオリジナル・プロジェクト「G.J.JUKE」によるギグで、2月17日横浜サムズ・アップを皮切りに都内や藤沢を廻り、締めくくりが28日渋谷クロコダイル、それらの日程の間に関西圏に足を伸ばすというスケジュール。まあ、なんとかなるだろう位の軽い気持ちで組んだこの日程は、実際にスタートしてみるとかなりハードで、まるで日を追って重くなってゆく大きな荷物を背負ったまま全力疾走するような、そんな毎日の連続だった。十分なリハーサルを持つことが時間的にどうしても無理で、全演奏曲、特にオリジナル曲の仕上がりが思い描いてるイメージになかなか近づけることができないのが一番辛い。それでも日々いろいろなアイデアや工夫を考え、毎回のギグでそれらを試しては少しでも音に反映させようと試行錯誤を繰り返した。ここまでしてかたくなにオリジナル曲を中心にしたショーを続けたのは、この短期間内にミュージシャンである俺個人としてもG.J.JUKEというユニットとしても、少しでも成長し、充実し納得できる気分で締めくくりを迎えたかったからだ。
そんな状況の中、やや過剰な頑張りすぎがたたり、肉体的にも精神的にも疲れが溜まってゆく毎日を送るうちに、「無理だ。」というあきらめや「こんなもんだろ。」という言い訳、そして「やっつけ仕事でさっさと片付けちゃおうか。」というような甘えが気持ちの中に生まれかかっていたのも確かだった。しかしそんなツアーもいよいよ締めくくり、2月28日クロコダイルでの演奏の直前に、「すいません、ヒロさんのオリジナルで『天国があったら...』と唄っている曲の題名を教えて下さい。」と、ある女性客が話しかけてきた。
「あぁ、あれは『願い』って曲。でもどうして俺のオリジナルを知ってるの?」と尋ねると、彼女が俺のショーを最初に観たのは初日の横浜サムズアップで、そもそも他のメンバーの演奏を聴くのが目当てで足を運んだだけで俺のことは全く知らなかったが、そこでたまたま聴いた「願い」がひどく気に入り、スケジュールをインターネットでチェックして、それ以来24日の藤沢ビートバー・ベック以外の全てのG.J.JUKEのショーに来ている、そして更に、「私にはとても親しかった幼なじみの思い出があります。彼は重い病気を患い亡くなりました。もし彼が生きていれば、間違いなく私たちは結婚していたと思う、それ位お互いが大好きだったんです。でも『願い』を聴いていると、彼が今でも私のそばにいて、私を見守ってくれてるような気がするんです。」と、曲名を尋ねた理由も彼女は話してくれた。
俺のオリジナルをここまで心に刻んでくれている人と出会えて、中途半端な気持ちでは絶対に音楽はするまいと激しく自分に言い聞かせると、背中の荷物がいっきに軽くなったように思えた。演奏が始まり、「願い」を歌いながら客席にふと目をやると、ハンカチで目を覆っている彼女の姿が飛び込んできた。こっちまで胸が熱くなって、唄い終わるのがやっとだった。
---「願い」---
もしも本当に天国があって あんたが住んでいるというのなら
いますぐここに降りてきて 俺の願いをかなえてくれ
解り合えないと思うだけで 違い過ぎると思うだけで
正しいと信じるだけで 間違っていると決めつけるだけで
傷付け合い絶望の涙を流し合う 悲しみを知らない人がいる
あんたはいますぐここに来て もうよしなよと伝えてほしい
言葉にならないやるせなさ 訳の解らない空しさ
鏡に映る自分を見れば 空っぽの手の中でうずくまっていた
ただの自分をあざ笑いながら 悲しい歌ばかり唄う俺がいる
そんな時あんたがそばに来て 大丈夫だよと肩を叩いて欲しい
最後の願いを聞いて欲しい これが本当に最後だから
とても大切な願いだから どうしてもかなえてほしい
酒臭い店でギターを弾いて 古臭い歌ばかり唄う俺だけど
俺には大切な人がいる こんな俺を抱きしめてくれる人がいる
もしも俺が飲み潰れて押し潰されて あの人を守る事が出来なくなったら
そんな時こそあんたが彼女を守りながら 俺は幸せだよと伝えて欲しい
もしも本当に天国があって あんたが住んでいるというのなら
いますぐここに降りてきて 俺の願いをかなえてくれ
(2005年3月4日、詞曲;鈴木ヒロマサ)
***この日本ツアーでは、2月15日から3月8日までの22日間の滞在中に、結果的にはラジオ出演やセッション等々を含めて計15回のパフォーマンスを行なったことになる。行く先々で多くの人々との新しい出会いがあり、新しい音楽が生まれ、それら一つ一つが将来大きな大きな意味を持つことになりそうな予感がする。特に今回は、ジャム・セッションのハウス・バンドへの参加や、ギター・クリニック、そしてG.J.JUKE自らがハウス・バンドをつとめるセッションと、多くの若い才能との出会いに恵まれる機会を多く得られたことは、何よりの収穫だったと思う。
2月18日の渋谷テラプレインのセッションと、3月1日の大塚ウエルカムバックのジャム・セッションのハウス・バンドをつとめたのは、ブルース大好き青年たちによる「北川純とブルース青年会議所」という不思議な名前のバンド。この二つのセッションを通してめぐり会った、ハウス・バンドを含む多くのミュージシャンの中では、何故か女性の存在感が際立っていたように思える。ウエルカムバックのジャム・セッションに飛び入りしたチェリーレッドのギブソンSGスペシャルが妙に板に付いていた女性は、不器用にかき鳴らすギターのトーンが何故かとても耳に心地よく、かっこよかった。ギターが大好きでロックが大好きでブルースが大好きでなければ絶対に生まれないトーンだ。テクニックや知識云々ではなく、どんな音楽をやりたいのかがひしひしと伝わってくるような演奏。彼女のようなプレーヤーがもっと多く出てきてほしいと思う。また、ギター、ドラム、ベースといったベーシックなセクション以外の楽器奏者の参加が非常に少ない中、ただ一人のピアニストがセッションに加わってくれた時はとても新鮮な気分だった。その女性ピアニストもまた、音楽する喜びを満面に浮かべてプレーをしていたのがとても嬉しい。
もう一人、「ブルース青年会議所」の一メンバーとして、両方のセッションでプレーした金澤沙織というドラマーがいた。すでにテラプレインのリハーサルの段階で、特にグルーヴを生み出すという点で飛び抜けていた彼女に、最初のセットの前に「俺はいつもドラマーにぴったり貼りつくギタリストだから、今回もあなたのグルーヴに乗せてもらうから。落とすところはスティックを置いちゃうくらい落として、盛り上げるところは徹底的にぶったたいて、ダイナミズムを思いっきりつけて。合図は送るけど、お互いが思ってることを感じるようにしよう。」と話した。彼女はよく理解し、注意深くキューをとらえ、安定したグルーヴとダイナミズムで素晴らしいバックアップをしてくれた。ただ初めてのコンビネーションだったこともあり、それぞれの曲やソロがどういう形や色に仕上がってゆくのかが明瞭でなくなった時に、どうしても周りに合わせすぎてしまう感があったので、「誰かがカウントを出したから曲を始めるんじゃなくて、『自分が曲を始める』からカウントに乗るし、誰かが合図を出したから終るんじゃなくて、『自分が曲を終わらせる』からエンディングのフレーズを叩く、つまり『自分はこの曲を創造するコンダクターなんだ。』位の気持ちがあって丁度いいと思うよ。だから、もし『あれ、ヒロさん、もっとソロを盛り上げてよ。』って思ったら、俺をどんどん煽ってごらんよ。」と再びファースト・セットの後に話した。
こんなふうにしてテラプレインでもウェルカムバックでも、ほとんどのセットの後に感じた事を俺なりに伝え、まるでそれらの意見に正確で丁寧な回答をするかのように、彼女の演奏はセットを追うごとに存在感を増していった。そしてウェルカムバックのセッションの後、今度は彼女の方から、「ヒロさん、みんなソロとかでおとなしすぎると思うんですが、ジャムってこんなもんなんでしょうか? もっとガンガンいっていいと思うんだけど。」という嬉しい(?)意見が出た。ただ楽曲をみんなで合わせるだけではいい音楽は絶対に生まれっこない、時にはメンバーどうしの情熱とか情念とかが音を伝わってぶつかり合い、火花を散らし、時にはいたわり合い、時には愛し合う、つまりワンツースリーフォーとカウントが出た途端に仲良く無難にエンディングまで辿り着こうとするのではなく、次の瞬間に何が起来ても不思議ではない、緊張感のあるエネルギーがステージから発せられ、それが観る側をも巻き込んだ時にこそ素晴らしい音楽が生まれるのではないだろうか、という持論を話し、今回の日本滞在中最後のG.J.JUKEによるセッションである
3月8日の新中野「弁天」にドラムスティック持参で必ず遊びに来るようにと伝えた。
今回の帰国で出会った若く素晴らしい才能を語る時、どうしても紹介しておきたいミュージシャンがもう一人いる。...このコラムを御読みになっている皆さん、前出の金澤沙織同様、どうか彼等の名前を絶対に忘れずに、チャンスがあれば実際に彼等の演奏を聴いてみて欲しい...それは20歳になったばかりのギタリスト兼シンガー、藤倉嗣久(ツグヒサ;<http://www10.ocn.ne.jp/~matsu113/pe-ji2/hotoke1.htm>を参照)だ。2月17日横浜サムズアップでの対バンにと、ハーピストのコテツ氏から紹介されたバンド「ソウル・ステュー」のリーダーで、すでに永井隆、鮎川誠、塩次伸二、山岸潤史といったビッグ・ネーム達からも非常に高い評価を受けている。とても20歳とは思えない感情豊かな唄いっぷり、そしてなんといってもデレク・トラックス直系の超絶スライド・ギター・プレーは必見だ。ミュージシャン=アーティストとして不可欠な感性、それぞれの曲をどんな色に染めたいのか、どんなシェイプに仕上げたいのか、そうするためにメンバー一人一人にどうして欲しいか、を常にピクチュアライズし、バンド全体を引っ張るのに十分な実力と大きな存在感がある。彼にも3月8日にはギター持参で必ず参加するように誘ったところ、「自分のアンプを持って行っていいですか?」という、涙が出るほど嬉しい二つ返事が返ってきた。
話が大きく前後するが、2月19日「楽や」でのアコースティック・セッションの後、最高にリラックスした気分で酒を飲んでいると、G.J.JUKEのドラマー、嶋田吉隆氏が、「オマエ、3月9日に(NYに)帰るんだろ、なんで3月中にギグを一本も取らないで2月28日で締めくくるんだよ?」と言い出した。「だーってヨシさん、3月の最初の週末(3,4,5日)はチャーのツアーで忙しいって言ってたじゃん?!」と答えると、今度はその隣にいたベースの渡辺茂氏がすかさず「7,8なら、俺、空いてるよ。」と話に加わり、二人で「どっか、今からでもブック出来ないかなぁ?」とかぶつぶつ言いながらいきなり電話をかけ始めた。NYへのフライトは3月9日午前11時である。最後の3日間はゆーっくりと実家でくつろごうと楽しみにしていた。
「ちょ、ちょっと待って、7,8はオフなんだけど...9日の朝はもう成田だし...」などと言っても、二人の耳にはぜんぜん届いていない。強力にグルーヴしはじめた40代リズムセクションを止める事は出来なかった。「取れたよ。8日、新中野、弁天。」、「あぁ、あの店は良いよ、やったじゃん。」、「ヒロ、何日に帰るんだっけ?えっ、8日?、フライト何時?11時?空港までは?バス?じゃあ、7時頃出ればいいんだろ?心配すんな、朝まで付き合ってやっから。」とかなんとか言いながら、二人は涼しい顔で満足げにビールを飲み続けている。酔った勢いでブックされた帰米直前の3月8日新中野「弁天」、これが本当の締めくくりセッションになったわけだ。
弁天はモダンなオフィスビルの地下にあり、まだ開けて間もないという事で、ブルースやロックというよりむしろ、おしゃれなジャズやフュージョンとかが似合いそうな、都会的な雰囲気のライヴ・ハウスだった。機材や音響設備が非常に充実しており、また店全体が音に集中できる無駄のない造りがとても気に入った。ここでのショーは、ファースト・セットがオリジナル中心のG.J.JUKEのセット、そしてセカンド・セットが多くのゲストを交えてのインヴァイティッド・ジャム・セッションとした。山田智之という最高にかっこいいパーカッション・プレーヤーがノーギャラを承知でセカンド・セット中叩きまくっていたし、高橋誠がテレキャスター・カスタムの弦をぶっちぎってブルースを弾いたし、昨年ニューヨークの有名クラブ「カッティング・ルーム」のジャムに飛び入りし日本語でビル・ウィザースの「リーン・オン・ミー」を唄い、満員の観客を総立ちにさせた森永アキラがこのセッションでも素晴らしい歌を聴かせてくれた。オーディエンスの中にはギブソンSGスペシャルのブルース・ウーマンやかつてNYで俺や嶋田氏と同じサーキットでプレーしていたことのあるドラマーのキンヤもの姿も。
そしてこの晩、ステージに注がれる二つの大きな大きな視線を、ファースト・セットの一曲目から痛いほど感じていた。ステージ上手のカーテンの隙間から噛み付くように見つめる藤倉ツグヒサと、客席のずっと奥のほうから大きな瞳を光らせる金澤沙織。最初はツグヒサがステージに上がり、3曲ほど演奏し、その後、嶋田氏に代わって沙織がG.J.JUKEに参加。どちらの演奏も本当に素晴らしかった。各自の演奏が終わった後も、二人共熱心に演奏を聴き続け、その晩の最後の曲では沙織とソウル・ステューのドラマー吉岡優三がいつの間にかステージに上がり、山田智之と三人でパーカッションを叩きまくっていたのには思わず笑ってしまった。(沙織のコンガがこれまた素晴らしい。)
ニューヨークでジャム・セッションに参加する場合、時には驚くほどのキャリアを持つミュージシャンとの偶然の共演が実現する可能性がある。今までの経験を例を挙げるならば、リッチー・キャナタ(ビリー・ジョエル・バンド、ビーチ・ボーイズのサキソフォン)、クラッシャー・グリーン(故人、元ウイルソン・ピケット・バンドのドラマー)、スティーヴ・ローガン(ハイラム・ブロックス・バンドのベース)、ダニー・ドレイヤー(エッタ・ジェイムス・バンドのギター)、ディヴィッド・コーエン(カントリー・ジョー・アンド・ザ・フィッシュ、マイケル・ブルームフィールド・バンド、ミック・テイラー・バンドのキーボード)、トッド・ウルフ(シェリル・クロウ・バンドのギター)、ジョン・パリス(ジョニー・ウィンター・バンドのベース、ハープ、ギター)等々、枚挙に遑がない。彼等にしてみれば、ほとんどは他のセッションやギグの帰り道にたまたまふらりと立ち寄ったり、ジャムを仕切っているハウス・バンドのメンバーやライヴ・ハウスの店員とかに知り合いがいるから一杯引っ掛けに寄った、そしたらバンドから「プレーしてくか?」と誘われ、たまたま気が向いたから、じゃあ弾いてこうか、せいぜいその程度のきっかけで気軽に飛び入りしてくるのだろう。
でも、どんなに小さなチャンスでもいいから手に入れようと手当たり次第にジャムに参加する駆け出しぺーぺーのこっちの立場にしてみれば、彼等との演奏そのものが夢のような経験であるのはもちろんだし、なによりも大きいのは、彼等のようなトップクラスのミュージシャンとのセッションを通じて、今の自分のプレーには何が必要なのかをより明確に具体的に発見できる、言い換えれば自分の演奏をより客観的に見つめられる絶好の機会であるということ、そしてもう一つは、どんなにリラックスして演奏していても、彼等が音楽と向き合ったときに必ず生まれてくる独特の緊張感を新鮮に体験できる絶好の場であるということだと思う。
ジャムの始まる随分前に店にやってきて、セッション・リストのなるべく上のほうに名前を書き、なんとか早く演奏したいと順番を待つ参加者達も、ずっと後からやってきた彼等が順番を飛び越してセッションに参加しても誰も文句を言わない。それがこの実力第一の世界の「あたりまえ」だからだ。タイミングよく彼等とセッション出来れば万々歳、時にはリストの一番上に名前を書いて4時間も5時間も順番を待ち、とうとう一曲も参加できずにジャムが終ってしまう事だってしばしば、それでも懲りずにジャムに通う。なぜならそこには自分を次のレベルに導くチャンスが少なからず存在するからだ。
数年前から帰国の毎に出来るだけ多くのジャム・セッションに足を運ぶようにしている。今回のウエルカムバックでは、国内では初めてハウス・バンドのメンバーとしてジャム・セッションに参加した。どれもハウス・バンドやホスト役によってきめ細かにリードされ整理整頓され、参加者全員を平等に演奏させるようにとの細心の努力が施されていた。参加者の中にはかなりレベルの高いミュージシャンもいるが、総じてミュージシャンどうしのコミュニケーションが希薄で、なんだかそれぞれがバラバラに自宅の居間でCDに合わせて楽器を弾いているような、フラットで緊張感に欠ける演奏がほとんどだった。そして現役プロとして頻繁にライヴ・パフォーマンスをこなすようなプレーヤーがそこに飛び入り参加するような場面には残念ながら一度も遭遇した事がない。
ビッグ・ネームと呼ばれるミュージシャンのライヴ演奏を、それも彼等の汗が届くほど小さなスペースで経験すればはっきりとわかることだが、鳥肌の立つような緊張感とジェット・コースターのようなダイナミズムがそこに必ず存在する。そしてどんなに優秀なレコーディング技術や再生技術をもってしても、それらを再現する事は絶対に無理、つまり良いライヴ演奏を経験したければ、良いライヴ演奏の場に自分を投げ込む他に手段はないのである。弁天でのセカンド・セットを、インヴァイティッド(招待制)ながらもジャム・セッションとし、今までに日本で出会った多くのミュージシャンにプロ、アマ一切問わず声をかけた大きな理由の一つは、日本のR&B、ファンク、ロック、ソウルのシーンでバリバリに活躍するG.J.JUKEのメンバーの演奏を汗の十分届くスペースで経験し、チャンスがあれば共演できるような場を提供する事で、ニューヨークのジャムで経験してきたこような「緊張感」や「ダイナミズム」を少しでも日本にも伝えられないだろうか、と考えたからだ。
ニューヨークやシカゴ、ニューオリンズで「おい、あいつの演奏を聴いたか?」と聞かれれば、十中八九「あいつ」の演奏をライヴ・ハウスで聴いたかどうかを問われていると思って間違いない。これはいかにライヴ音楽がこれらの街に定着している(いた)かを物語っていると思う。今回の帰国で、東京や大阪には驚くほど多くのライヴ・ハウスがあることがわかり、とても喜ばしい限りだ。才能豊かなミュージシャンも多いのだから、後は我々がオーディエンスにまわったときにいかに「聴く」かで、日本のライヴ・ミュージック・シーンの盛り上がり方も、今とは随分と違ってくるのではないだろうか。
オーディオ側に大きく寄りすぎてしまった音楽の重心をライヴ・パフォーマンス側になんとかして引き寄せられるように、アマチュア・ミュージシャンがプロのライヴ・ミュージシャンと至近距離で演奏を通して交流出来る場を、もっと頻繁に設けられたら、とつくづく思ってしまう。(つづく)

写真その1
2月19日、東京都内で俺が一番リラックスできる店「楽や」でのアコースティック・セッション。言わずもがな、このリズム・セクションは世界中どこへ持って行っても恥ずかしくない。
![1[1] (2)a-3.jpg](http://www.pci-jpn.com/hirosuzuki/archives/1[1] (2)a-3.jpg)
写真その2
さてと...、一服しよ...電池...舌がビーリビリしまっせ...
ヒロ鈴木のWebsiteはこちら
ヒロ鈴木のVideo映像はこちら
ヒロ鈴木のインタビューはこちら
投稿者 hirosuzuki1 : 2006年04月21日 13:28